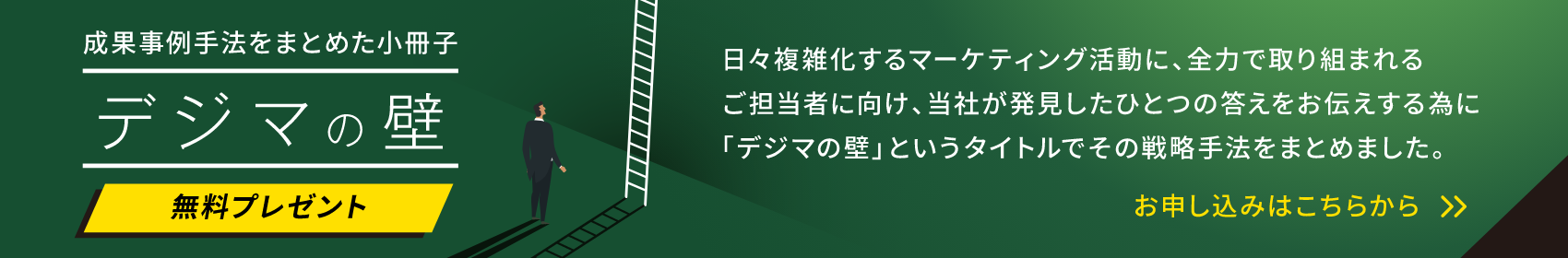Z世代が再定義するショッピングモールとは
March 12.2025
ピーク時には市場規模が10兆円に達していた百貨店市場は、現在では4兆円を下回っており、その縮小傾向は止まることを知りません。
最近の各社の対策として、百貨店という枠にとらわれず、自社の強みを明確に打ち出した「色」をつけることや、「コンシェルジュ」などのサービススタッフを充実させるモノではなく「コト」に特化したサービスへの転換が進んでいます。
その背景には、Z世代のショッピングセンターに対する価値観の変化があります。
この点について、以下の記事で取り上げられています。
https://tabi-labo.com/311038/lll022
この記事では、Z世代は百貨店やショッピングセンターを単なる買い物の場ではなく「つながり」を求める場として捉えているとのことです。
この「コミュニティースペース」の考え方は、Z世代だけに限ったものではなく、昭和の時代からも語られてきたことですが、デジタルネイティブのZ世代にとっては、より多くの一人の時間を過ごすことが多いため、他の人との関係を深める機会が限られています。
そのため、ショッピングセンターに出かけて、オンラインで知り合った人に会ったり、お店の店員さんと会話を交わすことが、孤独を解消する手段となっているようです。
このような背景から、モノの販売と同時に、スタッフとの関係性を深める機会や体験を提供することがますます重要になっています。
例えば、洋服の販売においては、コーディネートの提案を徹底的に行い、今までにない自分を体験した上で、商品を購入してもらうという店内オペレーションの強化が不可欠です。
109世代で話題になった「ハウスマヌカン」の役割が再度必要になってくるのでしょう。
先ほども記載しましたが、これからの小売業は、モノを売ること以上に「コト」を消費してもらうアイデアが求められる時代だと感じます。
最近の各社の対策として、百貨店という枠にとらわれず、自社の強みを明確に打ち出した「色」をつけることや、「コンシェルジュ」などのサービススタッフを充実させるモノではなく「コト」に特化したサービスへの転換が進んでいます。
その背景には、Z世代のショッピングセンターに対する価値観の変化があります。
この点について、以下の記事で取り上げられています。
https://tabi-labo.com/311038/lll022
この記事では、Z世代は百貨店やショッピングセンターを単なる買い物の場ではなく「つながり」を求める場として捉えているとのことです。
この「コミュニティースペース」の考え方は、Z世代だけに限ったものではなく、昭和の時代からも語られてきたことですが、デジタルネイティブのZ世代にとっては、より多くの一人の時間を過ごすことが多いため、他の人との関係を深める機会が限られています。
そのため、ショッピングセンターに出かけて、オンラインで知り合った人に会ったり、お店の店員さんと会話を交わすことが、孤独を解消する手段となっているようです。
このような背景から、モノの販売と同時に、スタッフとの関係性を深める機会や体験を提供することがますます重要になっています。
例えば、洋服の販売においては、コーディネートの提案を徹底的に行い、今までにない自分を体験した上で、商品を購入してもらうという店内オペレーションの強化が不可欠です。
109世代で話題になった「ハウスマヌカン」の役割が再度必要になってくるのでしょう。
先ほども記載しましたが、これからの小売業は、モノを売ること以上に「コト」を消費してもらうアイデアが求められる時代だと感じます。