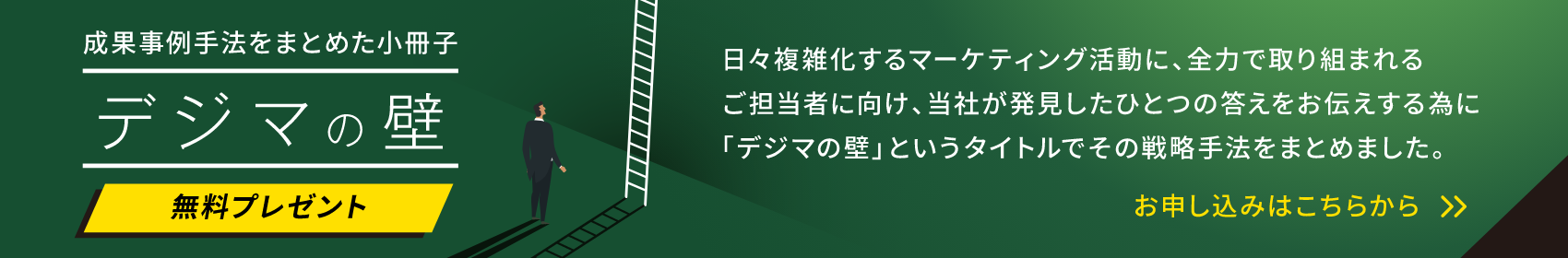『AIの民主化』が本番フェーズへ。Googleの新戦略が示す、業務と検索の未来図
November 10.2025
「またAIの話か…」と食傷気味の方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、最近のGoogleの動きは、AIが「一部の専門家のもの」から「全従業員のもの」へと、その立ち位置が決定的に変わる節目を示しているように強く感じています。
以前からお伝えしている通り、今後の最大のテーマの一つは『AIの民主化』であると考えられますが、それがより具体的に『業務のAIエージェント化』として本番フェーズに入ってきた印象です。
象徴的なのが、Googleが10月9日に発表した企業向け新サービス「Gemini Enterprise」です。
このサービスの核心は、専門家でなくても「ノーコード」で、つまりプログラム知識なしに、自社の業務を自動化するAIエージェントを構築できる点にあります。
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/2510/15/news032.html
これは、私たち中小企業にとって大きな意味を持ちます。
従来、AI活用は専門のエンジニアや高額なコンサルティングが必要な領域でした。
しかし、これが現場の担当者レベルで「自社のデータ」や「独自の業務フロー」(例えば、Google WorkspaceやMicrosoft 365、SAPなどの既存システム)と連携したAIを作れるようになるのです。
そして、この『AIの民主化』の波は、社内業務だけにとどまりません。
Googleの検索責任者であるリズ・リード氏が、先日The Wall Street Journalのポッドキャストで非常に興味深い戦略を語っています。
https://www.suzukikenichi.com/blog/redesigning-search-for-the-ai-era-liz-reid-on-googles-strategy-and-reality/
彼女は、AIによる検索結果の要約(AI Overview)が導入されても、広告収益は全体として損なわれていないと述べています。
むしろ、会話的な検索体験が「検索回数そのもの」を増やしているというのです。
ここで重要なポイントは、「ユーザーが情報を探す行動」そのものが変わろうとしている点です。
私たち事業者は、この変化にどう対応すべきでしょうか?
リード氏は、特に若年層が長文記事よりもショート動画やフォーラム(ユーザー生成コンテンツ)を好む傾向を認め、検索結果もそれに適応させていると語っています。
これは、従来のSEO対策やコンテンツマーケティングの前提を覆すものかもしれません。
この2つの動き(Gemini Enterpriseと検索のAI化)を合わせると、私たち中小企業にとって、以下のような具体的なビジネスインパクトが見えてきます。
1.既存業務プロセスの『AIエージェント化』
これまで人手に頼っていた定型業務(顧客対応の一部、データ集計、資料作成など)を、現場のスタッフが自らAIエージェント化し、劇的に効率化できる可能性があります。
2.マーケティング手法の根本的な見直し
ユーザーが「検索エンジンで調べる」から「AIと会話し、要約を得る」行動にシフトする中で、自社の情報(特に専門性や独自性)をどうAIに認識させ、AI Overviewやその先の「出典」として引用してもらうかが、新たな顧客接点として極めて重要になります。
3.新規事業モデルの創出
『AIの民主化』は、コストをかけずに新しいAIサービスを試作するチャンスでもあります。
ノーコードツールを使い、自社の強みとAIを組み合わせたニッチなサービス開発も現実的になるでしょう。
4.求められる人材スキルの変化
もはやAIは「作る」スキル以上に、「使いこなす」スキル、つまり「AIに的確な指示を出し、業務プロセスに組み込む」能力を持つ人材が組織の競争力を左右することになりそうです。
私たち中小企業は、この『AIの民主化』という大きな流れを「大企業の動向」と傍観するのではなく、自社の業務プロセスや顧客との接点をどう変革できるか、という視点で具体的に検討を始める時期に来ているのではないでしょうか。
鍵は「自社独自の強み(データやノウハウ)」を、いかにAIに組み込むかにあります。
ですが、最近のGoogleの動きは、AIが「一部の専門家のもの」から「全従業員のもの」へと、その立ち位置が決定的に変わる節目を示しているように強く感じています。
以前からお伝えしている通り、今後の最大のテーマの一つは『AIの民主化』であると考えられますが、それがより具体的に『業務のAIエージェント化』として本番フェーズに入ってきた印象です。
象徴的なのが、Googleが10月9日に発表した企業向け新サービス「Gemini Enterprise」です。
このサービスの核心は、専門家でなくても「ノーコード」で、つまりプログラム知識なしに、自社の業務を自動化するAIエージェントを構築できる点にあります。
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/2510/15/news032.html
これは、私たち中小企業にとって大きな意味を持ちます。
従来、AI活用は専門のエンジニアや高額なコンサルティングが必要な領域でした。
しかし、これが現場の担当者レベルで「自社のデータ」や「独自の業務フロー」(例えば、Google WorkspaceやMicrosoft 365、SAPなどの既存システム)と連携したAIを作れるようになるのです。
そして、この『AIの民主化』の波は、社内業務だけにとどまりません。
Googleの検索責任者であるリズ・リード氏が、先日The Wall Street Journalのポッドキャストで非常に興味深い戦略を語っています。
https://www.suzukikenichi.com/blog/redesigning-search-for-the-ai-era-liz-reid-on-googles-strategy-and-reality/
彼女は、AIによる検索結果の要約(AI Overview)が導入されても、広告収益は全体として損なわれていないと述べています。
むしろ、会話的な検索体験が「検索回数そのもの」を増やしているというのです。
ここで重要なポイントは、「ユーザーが情報を探す行動」そのものが変わろうとしている点です。
私たち事業者は、この変化にどう対応すべきでしょうか?
リード氏は、特に若年層が長文記事よりもショート動画やフォーラム(ユーザー生成コンテンツ)を好む傾向を認め、検索結果もそれに適応させていると語っています。
これは、従来のSEO対策やコンテンツマーケティングの前提を覆すものかもしれません。
この2つの動き(Gemini Enterpriseと検索のAI化)を合わせると、私たち中小企業にとって、以下のような具体的なビジネスインパクトが見えてきます。
1.既存業務プロセスの『AIエージェント化』
これまで人手に頼っていた定型業務(顧客対応の一部、データ集計、資料作成など)を、現場のスタッフが自らAIエージェント化し、劇的に効率化できる可能性があります。
2.マーケティング手法の根本的な見直し
ユーザーが「検索エンジンで調べる」から「AIと会話し、要約を得る」行動にシフトする中で、自社の情報(特に専門性や独自性)をどうAIに認識させ、AI Overviewやその先の「出典」として引用してもらうかが、新たな顧客接点として極めて重要になります。
3.新規事業モデルの創出
『AIの民主化』は、コストをかけずに新しいAIサービスを試作するチャンスでもあります。
ノーコードツールを使い、自社の強みとAIを組み合わせたニッチなサービス開発も現実的になるでしょう。
4.求められる人材スキルの変化
もはやAIは「作る」スキル以上に、「使いこなす」スキル、つまり「AIに的確な指示を出し、業務プロセスに組み込む」能力を持つ人材が組織の競争力を左右することになりそうです。
私たち中小企業は、この『AIの民主化』という大きな流れを「大企業の動向」と傍観するのではなく、自社の業務プロセスや顧客との接点をどう変革できるか、という視点で具体的に検討を始める時期に来ているのではないでしょうか。
鍵は「自社独自の強み(データやノウハウ)」を、いかにAIに組み込むかにあります。